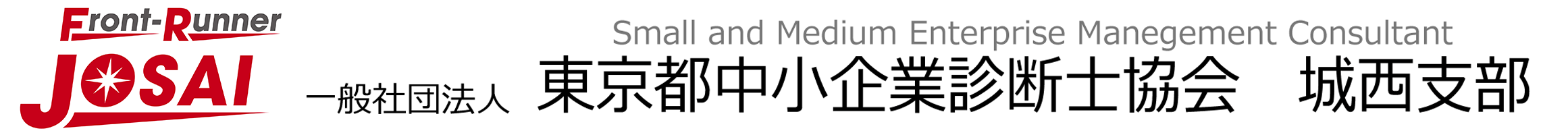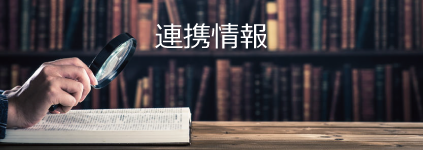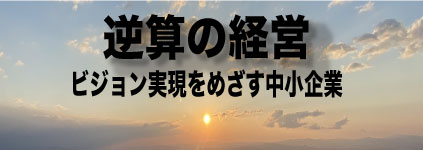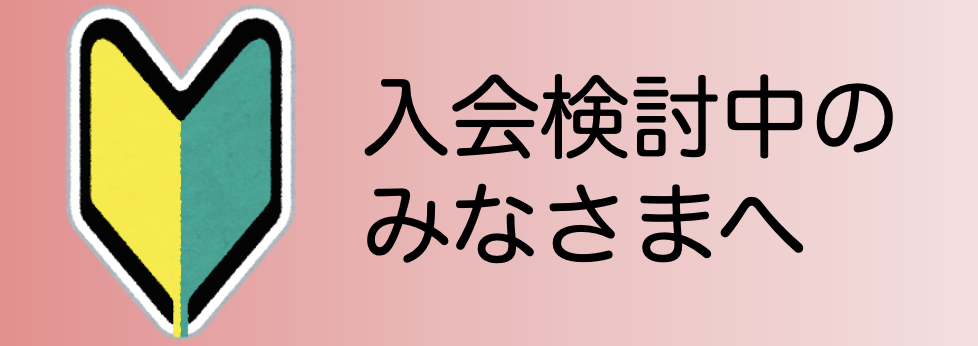10月18日、としま区民センター会議室にて令和7年度地域支援ゼミ第2回が開催されました。今回のゼミは地域支援部と社会貢献事業部との共催でした。参加者29名(外部参加者5名を含む)を集め、「共創型社会貢献活動について」をテーマに講演やディスカッションが行われました。
社会が抱える何らかの課題を解決するために行われる活動を広く「社会貢献活動」と捉えた上で、企業などが単独で実施する活動ではなく、企業、NPO、行政、商店街、大学、そして私たち診断士等々が連携・協働しながら、より良い社会を“共に創り上げていく”活動に焦点を当てたいとの意図から、あえて「共創型」という言葉を付けました。
外部から地域で活動しているNPO法人2団体の各代表(NPO法人テラコヤの前田和真様、NPO法人ブランディングポートの安藤奏様)ならびに各団体の活動・イベントに参加された大学生3名の方々にも参加いただきました。いずれのNPOも若者を対象とした事業を展開されており、学習あるいはキャリア形成に関する様々な支援を、企業や行政、大学等とも連携しながら行われています。その活動全体が社会貢献そのものとも言える団体の代表お二人に参加頂けたことは、とても有難く意義深いものでした。更に、私たち診断士が(少なくとも普段の診断士業務では)なかなか接点を持つ機会がない若い学生さんの参加も得たことで、どこか新鮮な雰囲気が感じられる場となりました。

ゼミの内容としては、まず地域支援部と社会貢献事業部からの活動紹介の後、各NPOの活動紹介をしていただきました。そして今回のテーマに即した実際の取り組み事例を3つ取り上げ、それらの簡単な説明の後、参加者を2つのグループに分け、ディスカッションを実施しました。参加者全員が積極的にディスカッションに加わり、活発な意見交換が行われました。

一般的に「ゼミ(ゼミナール)」とは、大学などで学生からの発表に加え参加者全員での討論を行うことにより、研究を深めていくことを目的に実施されるものだと思いますが、その意味でも、今回実施したような全員参加型のディスカッションをもっと増やしていくべきなのかもしれません。もちろん常に実施できるとは限らないと思いますが、それもまた今回得られた気づきの一つでした。
ゼミ終了後には、池袋の立教大学生が多く集まるレストランにて懇親会を行いました。各代表及び学生から普段聞けないようなお話を聞くことができ、とても有意義な時間となりました。