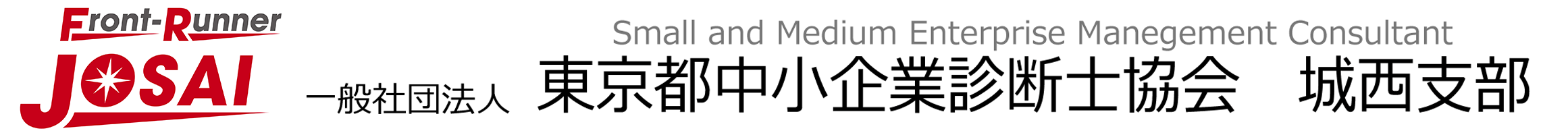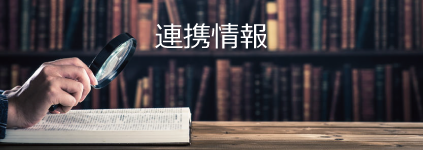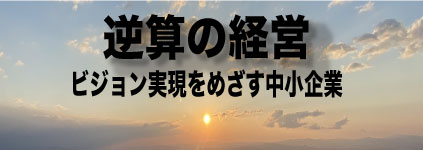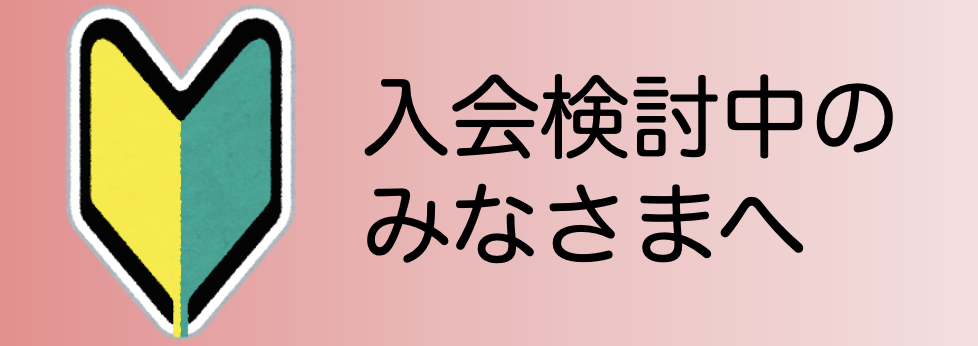#42 AKISHA株式会社 代表取締役 ロブ ヴァン ナイレンさん
日本経済は失われた30年という長い停滞を経験し、強みとしてきた製造業も厳しい環境にさらされています。近年、ものづくりを支えてきた中小企業の経営者の高齢化が進み、蓄積されてきた技術・事業の継続が危ぶまれています。AKISHA株式会社は、事業承継に課題を抱える中小製造業を買い受け、事業の存続・成長を図っていくことを目的とする会社です。本年同社を設立されたヴァン・ナイレン代表取締役に日本のものづくり再生に向けた取り組みについて伺いました。
欧州から見た日本の強みと弱み
― これまでのお仕事と今般貴社を立ち上げられた経緯を教えてください
ヴァン・ナイレン 私は1980年代に母国ベルギーのカトリック・ルーヴァン大学日本語学科で学んでいました。当時、日本の目覚ましい経済発展を欧州では誰も説明できませんでした。自分自身で日本を研究したいと思い、竹下首相当時、ベルリン日独センターの奨学金で関西大学に1年間留学しました。母国に戻って大学院で経営学を学び、卒業後に欧州の日系自動車メーカーの新規JV会社で4年間勤務しました。
その後1996年に来日し、欧州企業向けに日本市場参入、事業拡大、業容見直しを支援する事務所を東京に立ち上げました。多くの日本企業と欧州企業と仕事すると共に、欧州連合や王立ベルギーサッカー協会などの公的機関の日本での事業も受注してきました。これまで日本で数多くの仕事をしてきましたが、今、その日本は事業承継という大きな課題に直面しています。2025年に中小企業の経営者の約245万人が70歳を迎え、その半分以上で後継者が未定の状況です。すばらしい日本のものづくりが消えてしまうのは日本だけでなく、全世界の損失です。
このような危機感の下、お世話になってきた日本への恩返しの気持ちを強く持って、中小製造業を次世代に残すことをミッションとするAKISHA株式会社を2025年3月に設立しました。

代表取締役CPSOのロブ ヴァン ナイレンさん
― 日本の中小製造業の課題をどのように分析されているでしょうか
ヴァン・ナイレン 日本のものづくりは変わらず世界に通用する高いレベルにあります。例えば、2020年東京オリンピックで授与された日本製メダルの光沢・品質のよさは他国製メダルと比較して一目瞭然です。最近、欧州から日本を訪問した企業経営者は、一度廉価なアジア製機械に乗り換えたが、結局品質の高い日本製に戻ったと語っていました。海外から見て日本製のブランド力は依然高いです。
しかしこのまま何もしないと、劣化していくと強く危惧しています。日本の中小製造業は、ものづくりは上手ですが、バックオフィス機能が非効率で、DXやAIの活用といった効果的な管理業務の導入が遅れています。また、下請関係からの脱却も進んでいません。取引先から提示された価格、納期を受け入れ、給料も上げられず、土日も働き、いくら働いても十分な利益をあげられていない状況です。
海外市場への展開も遅れています。日本の人口はピークを越え、これからの減少スピードが加速します。そのような中、顕著な円安局面でありながら、海外市場になかなか目がいかないことは課題だと思っています。そして大きな問題が後継者不足です。若い人の持つ不透明な将来、3Kという製造業のイメージを変えていく必要があります。
経済の“空き家”を埋める
― 厳しい状況認識がありますが、AKISHAはどうやってものづくりを強化していくのでしょうか
ヴァン・ナイレン AKISHAは、後継者がいない製造業、将来の事業承継に不安を抱える企業を中心に株式を過半数以上取得し、共同経営者となります。引き取り手がいない空き家問題で、古い建物の価値に気づき、活用・継承を始めたのも外国人でした。同様に「空き社」となりかねない価値ある会社を1社でも多く次世代に残すという会社の理念を「AKISHA」という社名に込めました。
AKISHAは地方を含めて、国内の魅力的なものづくり企業を残していければと考えています。買い受けたものづくり企業を継承していくためには、それが魅力的な仕事であることが再認識される必要があります。適切に利益をあげて十分な給料と休みが得られ、海外とも仕事ができる職場であれば、若い人も製造業に目を向け、地方にも残るでしょう。
対象は金属、プラスティック、機械、電気・電子といった分野で、海外市場を目指せるものづくり企業です。他のM&A会社やファンドとは異なり、基本的に再譲渡はせず、共に長期成長していくことを目指します。各企業は強みであるものづくりに集中してもらい、AKISHAが保有会社全体へバックオフィスサービスを提供します。管理業務を共通化することで効率化が可能となります。連結決算により、金融機関との交渉力も高まります。

空き社に取り組み、ものづくりを次世代に残す
その上で、営業・売上拡大に取り組みます。当社は主要海外市場の現地パートナーとの協力関係を構築しており、AKISHAのジャパン・ブランドを海外各国に販売します。また、顧客との下請関係を改善し、プライステイカーからプライスセッターへ改善することに取り組みます。従来の取引を大事にしながらも、外部共同経営者として、これまでの関係ではできなかった交渉ができることが強みになるでしょう。このビジネスプランは練馬ビジネスサポートセンターの企業創業セミナー(ねりま塾)で練り上げ、令和6年度の審査員特別賞を受賞しました。
「スイミーの黒い目」で強い企業体に
― どのようなものづくり企業を目指しますか
ヴァン・ナイレン 事業承継問題の解決、管理業務の効率化、海外への販路拡大、適正な取引関係の構築により、営業利益率2桁を達成し、世界に通用するものづくり企業グループを作り上げます。AKISHAはグループの方向性を示し、ビジネスの実行を指揮する司令塔となり、グループ内の企業は強みである日本のものづくりを磨き、実践します。
これまで、多くの製造業グループは垂直統合型でした。AKISHAは縦ではなく、横のつながりによって、強みを出していくグループを志向していきます。有名なレオ・レオニの絵本「スイミー」は、数多くの小さな魚たちが皆で大きな魚の姿となって泳ぎ出し、大魚に挑む話ですが、リーダーの小さな黒い魚が小魚たちを取りまとめ、全体の黒い目となってそれを実現しました。これと同様にAKISHAはスイミーの黒い目の役割を果たします。
加えて生きがいと志の社風を重視します。給料も休みも少ない、という製造業のイメージを排し、若い人や女性が活躍、成長できる企業を作りたいと思っています。特に女性は語学力が高い人が多い一方で、仕事に十分に活かせていないと感じています。日本でのローカルなものづくりをグローバルな人材が活躍して、世界に通用するものづくりグループを作ります。

中小製造業の目となり、グローバル・オーシャンへ
― 具体的な実行方法について教えてください
ヴァン・ナイレン 承継する中小製造業は技術力と製品力があり、海外展開が可能であることを重視します。買収にあたり、黒字経営を行っていることも大事ですが、収支の状態のみを絶対視していません。譲渡者である経営者としっかりとコミュニケーションを取ってグループに入っていただきたいと思っています。
なお、日本には恥の文化があります。経営者は困っていることを直前まで周りに言いません。AKISHAは「見える化」だけでなく「話せる化」を大切にし、事業承継に悩む経営者が相談しやすい、二人三脚の伴走者になれればと考えています。企業名はブランド名ですから、譲受後も変更せず、旧経営者にもできるだけ残ってもらい、共に企業を運営できればと思っています。
バックオフィス機能に関しては、多くの中小企業は個社・業務レベルで取り組んでいますが、必ずしも顕著な成果はあがっていません。グループレベルで人事、経理、法務、マーケティング・営業、資金調達、広報等を統一し、効果を生み出します。
ものづくりと販売は外部、問屋に依存するだけではなく、関係を構築している海外パートナーと連携し、グループ内でも直接行います。これによって利益率の向上を実現します。グループ内企業のビジネス機会・顧客の融合、共同調達など、まだ目に見えない相乗効果もつくっていきます。
― 承継のための資金調達はどのように行うのでしょうか
AKISHAは各企業の年商から一定割合のバックオフィスサービス料を徴収します。資金調達はグループとしての信頼性を高めて、金融機関からの長期借入が中心となる見込みです。出資の受入は、将来一社でも多くグループに入ってもらうための資金調達手段としてはあり得ますが、第三者の参画によりAKISHAの理念が希釈しないよう、経営方針に影響しない範囲となるものと思います。
― AKISHAへの強い思いが伝わってきます。それを実現するためには、盤石な体制づくりが必要ですね
ヴァン・ナイレン AKISHAの経営陣は現在、外国人4名と日本人2名です。4名の外国人はいずれも豊富なビジネス経験と共に、長い間、日本にお世話になり、恩返ししたいとの思いを持っています。
私自身はCPSO(Chief Purpose and Sourcing Officer)という役割を担います。AKISHAの理念・経営方針というpurposeをぶれずに持ち、買取り企業の探索・選定、Sourcingを行います。他の役員は最高管理責任者、最高財務責任者、最高技術・オペレーション責任者、最終決定を行う最高経営責任者により構成されています。今後、企業を1社買い受ける毎に社員を1名採用する方針です。経営陣は若い人たちへのコーチング、アドバイジングを行い、若い力にAKISHAの実行を担ってもらいます。
また、AKISHAは世界の主要市場の現地パートナーとの関係を構築しています。いずれもAKISHAの理念に共鳴・共感しており、当社が扱う商材を積極的に扱う意思を持っています。ベルギー、フィンランド、アメリカ、メキシコ、インド等のパートナーを通して、AKISHAのジャパン・ブランドを主要市場に展開します。来年中にベルギーに欧州支社を設置する予定です。
ジャパン・ブランドの復活に向け今動く
― 目指すものづくりを実現するため、これから取り組むことは何でしょうか
ヴァン・ナイレン これから当社が取り組むべきことは4つです。第1に、AKISHAの信用をつくっていくことです。ものづくりを残すために取り組む真剣な企業であること、仲間になればよいことがあることを分かってもらうための説明・発信の努力を行っていきます。第2に、潤沢な資金調達を実現していくことです。多くの中小製造業にグループに参加してもらうためには、買い受けるための資金が必要です。円安が進んでいる中で、欧州からの資金調達も積極的に検討していきます。第3に、優秀な人材を確保・育成することです。これから長期で日本のものづくりを応援していくにあたり、若い人たちの存在・活躍が不可欠です。自分自身も先輩たちに教えてもらったように、若手の育成・サポートを行っていきます。第4に、事業の実績をつくっていくことです。海外で仕事を取り、売上をつくる。そして高い利益率を示していくことが重要です。
そして、何より第1号案件を実現することが必要です。中小企業診断士の方々には、事業承継に困難を抱える中小製造業の紹介、譲受後の企業の資金健全化、補助金の助言などで連携ができればと考えています。
これからAKISHAはスイミーの目となって1社でも多くのものづくり企業を牽引し、ジャパン・ブランドを復活・発展させていきます。仲間となる企業は、大事な子供を預かる意識でお迎えします。皆でグループとなって事業展開を共にし、長期にわたり成長していくことを目指します。そして、私自身、同じ船に乗る仲間のために全力で取り組んでいきたいと考えています。
※ 取材内容は2025年9月末時点のものです
|
[企業情報] |
(余禄)ものづくりを強みに経済成長を遂げた日本。その競争力の源泉、中小製造業は現在岐路に立っています。ものづくりを支えてきた技術・事業の多くが後継者不足で失われていく前に、世界からメイド・イン・ジャパンへの信頼がある今のうちに動かなければならない、とするAKISHA株式会社の取り組みは、ものづくりの将来を見据えた大きな逆算の経営です。日本への恩返しとして同社を設立されたヴァン・ナイレン代表取締役の日本への温かく、そして客観的な視点は、これからスイミーの目となって中小企業の進むべき道を照らし、ものづくり企業に勇気を与えるものと確信しています。(齊藤 幹也)